今の仕事がつらい・続けるのがしんどいと感じる人は少なくありません。
仕事を辞めたい気持ちが毎日募る一方、「自分が弱いだけなのか」「甘えていると言われるのではないか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「毎日仕事を辞めたいと思うのは本当に甘えなのか?」という疑問に焦点をあて、辞めるべきかどうかを判断するための基準や、実際に辞める際の注意点、さらには「退職代行」という方法についてもご紹介します。
毎日仕事を辞めたいと思うのは甘えじゃない
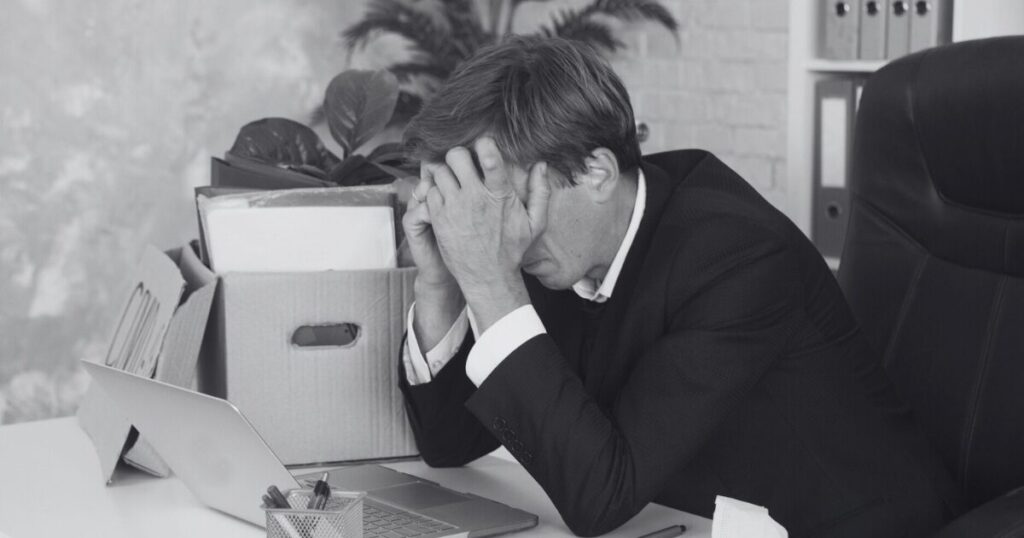
「仕事を辞めたい」と思う理由は人それぞれ
毎日仕事を辞めたいと思う理由は、人によって千差万別です。たとえば、人間関係のトラブルや、長時間残業・休日出勤が続いて疲労が抜けないこと、あるいは仕事内容が合わないことなど。これらの要因が複雑に絡み合い、「もう耐えられない」「このまま続けると心身が限界」と感じてしまうケースも珍しくありません。
一般的に「仕事を辞めたい」という発想は、「甘え」として片付けられがちです。しかし、実際には個人の置かれた状況や抱えるストレス、健康状態などによっては「辞めたい」という気持ちが正当なSOSである場合も多いのです。
感情だけでなく「体調」もチェックすべき
「毎日仕事を辞めたい」と考えるようになると、精神的なストレスだけでなく、身体面でも変化が起こりやすくなります。朝起きられない、胃痛や頭痛に悩まされる、夜眠れない、食欲がないなど、身体の不調が続いている場合は要注意です。疲れが抜けない状態で出勤を続けていると、うつ病や適応障害などのメンタルヘルス面にも深刻な影響が出るリスクがあります。
こうした「心身の不調」は、仕事からくるストレスのサインである場合も多いため、「甘え」だと自己否定するのではなく、まずは自分の状態を客観的に把握してみることが大切です。
「責任感が強すぎる」人こそ要注意
責任感が強く、周囲からの評価や期待に応えようとする人ほど「仕事を辞めたい」という気持ちを抱えていても、「自分が頑張れば解決できる」「ここで辞めたら迷惑になる」と我慢してしまいがちです。しかし、限界がきてから初めて「もうムリだ」と訴えるのでは遅すぎることもあります。
毎日「仕事辞めたい」と思い続けるレベルまで追い詰められているならば、一度立ち止まって「自分の心身は健康状態を保てているか」「このまま頑張り続ける意味があるのか」を再評価してみるのが良いでしょう。
仕事を毎日辞めたいと思いながら働くことのリスク
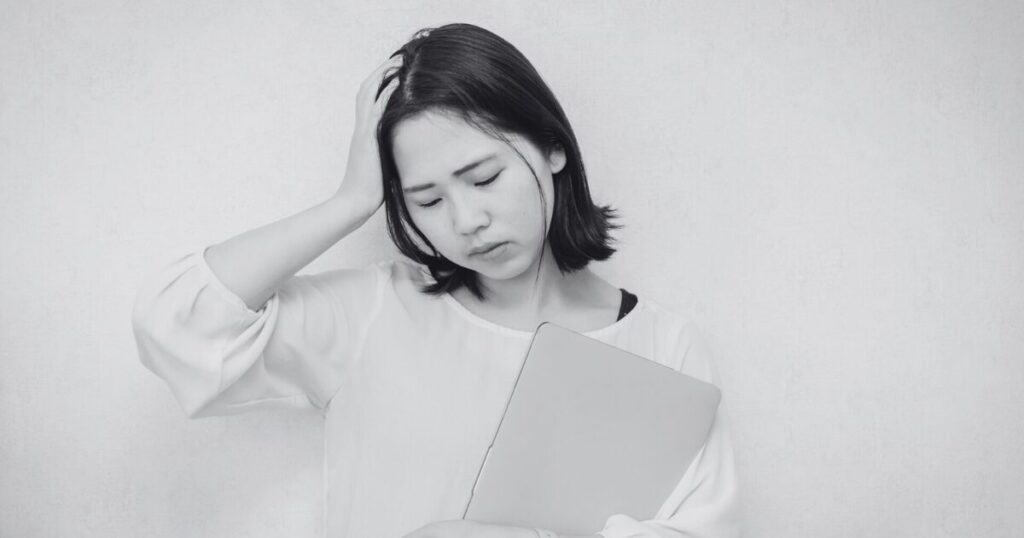
生産性の低下と評価の悪化
「仕事辞めたい毎日」という状態でモチベーションが下がっていると、仕事に対する集中力や意欲も低下します。毎日「辞めたい」「つらい」と思いながら働いていると、どうしても業務パフォーマンスが落ちがちです。生産性の低下は、結果として周囲からの評価にも影響を及ぼし、職場での人間関係や今後のキャリア形成にも悪影響を与える可能性があります。
メンタルヘルス不調や病気のリスク
前述のように、毎日辞めたいほど仕事がつらい状況に陥っていると、身体的にも精神的にも負荷がかかりすぎ、うつ病・適応障害・不安障害などの精神疾患にかかるリスクが高まります。一度、重度の精神疾患を発症してしまうと、回復までに時間がかかり、最悪の場合は長期休職や離職を余儀なくされることもあります。
「自分は大丈夫」と思っていても、気づかないうちにストレスが蓄積し、突発的に体調を崩してしまうケースも少なくありません。特に、日本の社会では「休むことは甘え」「仕事が忙しいのは当たり前」といった風潮が根強く、「どの職場でも同じだ」と思い込んでしまいがちです。ですが、異常なほどつらい状況が続いているならば、早めに対処策を検討する必要があります。
キャリアの停滞
毎日「辞めたい」と思いながら続けている状態では、新しいスキルの習得ややりがいを見つけるのも難しくなります。自分のキャリアを活かせる別の仕事に挑戦する気力が残っていない可能性もあり、ただ時間が過ぎていくことでキャリアが停滞してしまうリスクも考えられます。
キャリア形成においては「どの会社でどんな経験を積むか」が重要です。もし現在の仕事で得られる経験が、自分の目標や将来像にとって大きなプラスにならないと感じるのであれば、転職や退職を含めたキャリア戦略を立ててみる価値があるかもしれません。
仕事を辞めたほうがよいサイン

サイン1:体調不良やメンタルの限界が続いている
最初に確認すべきは、心身の健康状態です。頭痛や吐き気、めまい、不眠などの症状が仕事の前後で継続している場合、あるいは休日になっても疲れがとれず何もやる気が起きないといった場合は、明らかに仕事のストレスが大きい証拠です。こうした症状が長期間続くと、うつ病や適応障害に発展する恐れがあるため、限界を迎える前に退職や転職などの選択肢を考えてみるべきです。
サイン2:職場の人間関係が劣悪で改善の見込みがない
上司や同僚とのコミュニケーションがほとんど取れず孤立している、パワハラやセクハラがある、あるいは同僚間の足の引っ張り合いが常態化しているなど、人間関係が劣悪な場合も要注意です。人間関係の改善は個人の努力だけでは難しく、組織全体の風土が関わっていることも多々あります。
もし、上司に相談しても取り合ってもらえない、会社として改善する姿勢がまったく見えないという状況であれば、長く勤めるほどにストレスを溜め続ける結果になる可能性が高いでしょう。
サイン3:業務内容に大きなミスマッチを感じる
仕事そのものが自分の適性と合っていない場合も、早期に辞める選択をしてよいかもしれません。特に、入社前に聞いていた業務内容と大幅に違う業務を任されている、あるいは部署移動で全く興味のない領域に配属されたまま数年が過ぎている、といったケースは珍しくありません。
仕事は人生の大部分の時間を占めます。毎日嫌々こなす業務に時間と労力を費やすよりも、自分の得意な分野や興味のある分野で力を発揮できる環境を探す方が、長期的には本人のキャリアにとっても有益です。
サイン4:上司や会社に相談しても取り合ってもらえない
人事や上司に「忙しすぎる」「残業が多すぎる」「人間関係の問題がある」などの相談をしても、「みんな同じだから我慢して」「そんなの甘えだ」と一蹴されるようであれば、会社自体が労務管理に問題を抱えている可能性があります。こうした組織では将来的に環境が改善される見込みは低く、退職を検討した方が良いケースも少なくありません。
実際に仕事を辞める時の注意点

注意点1:次のキャリアプランを考えておく
「辞めたい」という気持ちがピークに達すると、衝動的に退職願を出したくなるかもしれません。しかし、仕事を辞める前に、できる限り次のキャリアプランを考えておくことが重要です。転職先を見つけてから辞めるか、あるいはしばらく休養期間を取るのかなど、自分がどう行動するかをある程度シミュレーションしておきましょう。
転職エージェントやキャリアコンサルタントに相談し、市場価値や求人状況を把握しておくと、スムーズに次の一歩を踏み出しやすくなります。
注意点2:引き継ぎと円満退職を心がける
退職を決めたら、会社への最終出社日から逆算して業務の引き継ぎを計画的に行いましょう。引き継ぎの段取りが悪いと、会社側もトラブルが増え、結果的に自分も気まずい思いをしたり、最終日までトラブル対応に追われたりしかねません。
特に、円満退職を望む場合は、退職希望日の少なくとも1ヶ月前には上司や人事に相談し、業務の整理や引き継ぎ書の作成などを行っておくことが望ましいです。
注意点3:有給休暇の消化方法
会社によっては、有給休暇が取りづらい雰囲気があるかもしれません。しかし法律的には、社員には一定日数の有給休暇が与えられるのが原則です。退職前にできるだけ有給を消化したいのであれば、その旨を会社に申し出ましょう。「消化できない」「その間の人員体制が確保できない」などの理由で拒否されることは、原則として違法です。
注意点4:在籍中に必要な書類を確認する
退職後に必要となる書類(源泉徴収票、離職票、雇用保険被保険者証など)がスムーズに発行されるよう、退職前に人事部・総務部と連絡をとっておきましょう。離職後、保険や年金の手続き、転職先での手続きなどに必要になる場合が多いため、早めに確認しておくと安心です。
改善されない時は「退職代行」もひとつの方法

「退職代行サービス」とは?
どうしても会社に直接「辞めたい」と言いづらい、上司に退職の意思を伝えても取り合ってもらえない、あるいはそもそも会社に行く気力がない――そんな状況で役立つのが「退職代行サービス」です。退職代行サービスは、本人に代わって退職に関する手続きを進めてくれる業者で、近年では法的トラブルに強い弁護士や労働組合が運営しているものも増えています。
退職代行を利用するメリット
- 精神的負担の軽減
直接会社と連絡を取らなくてもよいので、上司や同僚とのやり取りによるストレスから解放されます。 - スピーディーな退職手続き
会社によっては、退職願を出してから退職するまでに長い引き留めが行われることがあります。退職代行を利用すれば、最短で即日連絡をし、翌日以降に出社せずに退職が認められるケースもあります。 - 法律の専門知識を活用できる
弁護士法人や労働組合が運営している退職代行サービスを利用すると、法律的に正しい手続きで退職を進めてもらえるため、会社とのトラブルを回避しやすくなります。
退職代行を利用する際の注意点
- 信頼できる業者を選ぶ
退職代行サービスは多数存在しますが、中には実績が不明瞭な業者や、法的根拠をあまり理解していない業者もあります。料金体系やサポート内容、実績を必ずチェックし、信頼できるサービスを選びましょう。 - 弁護士が対応しているか確認
会社が「損害賠償を請求する」と言い出したり、未払い残業代やセクハラなどの労働問題に発展した場合、弁護士に相談した方が適切なアドバイスを受けられます。民間の業者でも労働組合型や弁護士法人型は、法律面の交渉能力が高いのが特徴です。 - 費用対効果を検討する
退職代行サービスの費用は3万円〜5万円ほどが相場ですが、弁護士法人の場合はそれ以上かかることもあります。自分が得られるメリット(上司とのコミュニケーション回避など)と費用を比較し、納得した上で利用しましょう。
もし現在の会社に出勤できないほど心身が限界で、退職の話すら持ち出せない場合は、こうした退職代行サービスの利用がひとつの選択肢となります。
まとめ
毎日仕事を辞めたいと思っている人の中には、「これくらいで辞めたら甘えなのでは?」と自問自答してしまう方も多いでしょう。しかし、毎日「仕事辞めたい」と思うほどのストレスや苦痛を抱えているなら、それは甘えではなく、心身が危険信号を発している可能性があります。
- まずは自分の状況を客観的に把握する
体調やメンタル面で限界がきていないかをチェック。会社の風土や人間関係などが改善できそうか検討する。 - 辞めるかどうかを判断する基準を明確化
「体調不良が続いている」「会社の労働環境に問題がある」「スキルアップやキャリア形成が望めない」など、自分にとって重大な問題かどうかを整理する。 - 転職先や次の行動プランをイメージしてから退職準備
衝動的に辞めるのではなく、転職先を探したり、退職後の生活をある程度シミュレーションしておくのが理想。 - どうしても改善されない場合は「退職代行」という選択肢も
会社に直接言いづらい、あるいは話が通じない場合は、退職代行サービスの利用を検討する。
仕事は人生の大きな時間を占めるため、「自分の努力が足りないだけ」と思い込み、無理をしてしまう人は少なくありません。しかし、心身を壊してしまえば、元も子もありません。毎日「仕事を辞めたい」と思ってしまうほど追い詰められているなら、一度立ち止まって自分の状況を冷静に分析し、必要であれば転職や退職を含めた解決策を検討してみてください。




コメント