「退職したいけれど、上司に退職の意思を直接伝える勇気がない」「会社と話すだけで胃が痛くなる」といった悩みを抱えている方は、近年増え続けています。
こうした背景の中、退職代行サービスの登場は多くの人にとって画期的な解決策となってきました。
一方で、退職代行を検討する人はパラハラなどに悩まされているケースも多く、「会社の人が自宅に押しかけてくるのではないか」といった不安もあるかもしれません。
本記事では、退職代行サービスの基本から、実際に「退職代行を利用したら会社が家に来る可能性はあるのか?」という疑問、そして「もし本当に来たらどう対処すればいいのか?」という点まで、専門性を意識しつつ分かりやすく解説します。
退職代行サービスとは?
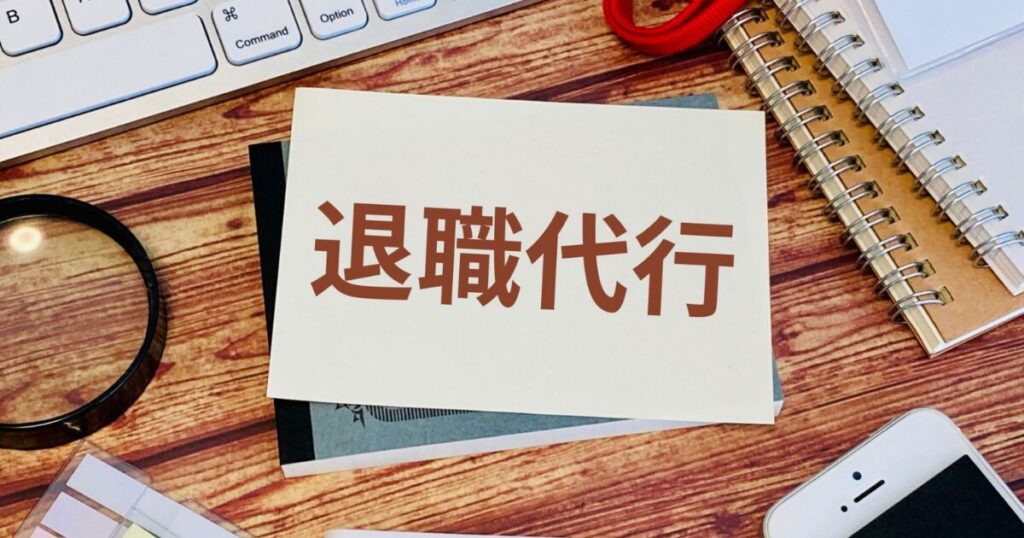
退職代行サービスは、文字通り「退職」にまつわる手続きを本人に代わって行ってくれるサービスのことです。一般的に、本人が会社に退職の意思を伝えたり、上司や人事担当者との交渉をしたりする必要がなくなるため、精神的・時間的負担を大きく軽減できるのが特徴です。
退職代行サービスの利用手順は、大まかに次のように進みます。ただし、具体的な手順や対応は各業者によって多少異なるため、あくまで目安として参考にしてください。
1. 相談・問い合わせ
まずは退職代行サービスのホームページやSNSなどを通じて、問い合わせフォームや電話で相談を行います。料金体系やサービス内容、サポート範囲などを確認し、自分の状況や希望に合うかどうかを検討しましょう。
2. 契約・支払い
利用したい退職代行業者が決まったら、契約内容を確認し、同意したうえで料金を支払います。業者によっては分割払いに対応しているところもあるので、予算とあわせて比較検討すると良いでしょう。
3. 情報提供・ヒアリング
契約後は、業者が退職を代行するために必要な情報をヒアリングします。たとえば会社名や勤務形態、就業年数、退職の希望日などを正確に伝えるとともに、今置かれている状況や悩みの背景を共有しておくと、より的確なサポートを受けやすくなります。
4. 会社への連絡・交渉
業者があなたに代わって、会社の上司や人事担当者に退職の意思を通知します。その後、会社とのやり取りが必要な場合(貸与物の返却や書類の受け取りなど)も、基本的には業者が間に入って対応してくれます。あなた自身が会社に連絡する必要はほとんどありません。
5. 退職手続きの完了
会社側が正式に退職を承諾し、離職票や源泉徴収票などの必要書類を受け取れば、退職手続きは完了です。会社が書類を郵送してくれることも多く、すべてのやり取りを退職代行業者が代行する場合は、退職届を提出してから一度も出社せずに退職が完了するケースもあります。
退職代行後、会社が家に来るケースはある?
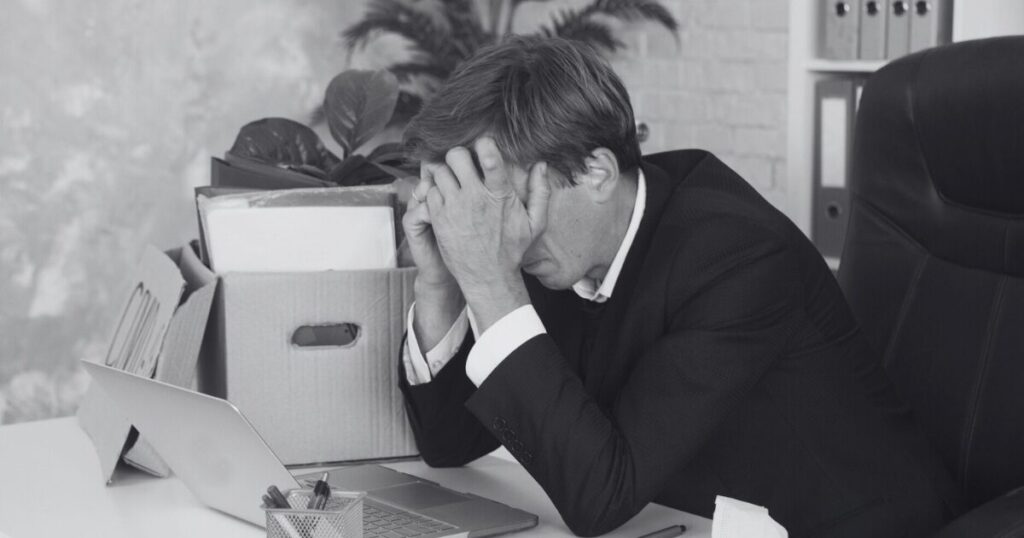
退職代行を利用するうえで、気になるのが「本当に会社が自宅に押しかけてくるのか?」という点ではないでしょうか。
実際のところ、会社が自宅を訪問するケースはさほど多くはないと考えられます。というのも、企業としては、わざわざ本人の住居を訪ねてまで問題を大きくしたくないのが一般的だからです。労働者の人権侵害やプライバシーの侵害と見なされるリスクをとってまで“家凸”する企業は、少数派だと言えます。
しかし、職場によっては社内ルールやコンプライアンスが浸透しておらず、経営者や上司が強引な手段で従業員を引き留めようとすることもあり得ます。
特に、いわゆるブラック企業や小規模で独善的な経営が行われている会社では、退職代行の通知に納得できず、本人に直接会って説得しようとする例がゼロとは言い切れません。
会社が家凸する理由とは?

それでもなお、実際に「退職代行 家凸」が起こり得るとしたら、どんな理由が考えられるのでしょうか。主に以下のようなパターンが想定されます。
1. 退職の意思を直接確認したい
上司や経営者が「退職代行なんか使わないで、直接話をしてほしい」「実際に本人が本気で辞めるのか確かめたい」という思いから、自宅を訪問してくる可能性があります。特に、優秀な人材に退職されると大きなダメージを受けるような企業では、直接話し合うことで退職を撤回させようとする試みがあるかもしれません。
2. 業務上の引き継ぎや書類の回収
会社から貸与されているPCや備品、重要な資料などが返却されていないまま、退職代行によって連絡が途絶えてしまった場合、会社としては「返却してほしい」と考えます。書類の不備や不足が残っていると、会社内部の業務に支障が出ることもあるため、やむを得ず社員の自宅を訪ねるケースがあり得ます。
3. 損害賠償や契約違反の確認
退職によって大きな損害が発生すると会社側が主張している場合や、競業避止義務のような契約条項が問題になっている場合には、直接会って話を聞き出そうとすることがあります。法的に見ても、退職代行業者が対応できる交渉の範囲は限られているため、会社としては本人に確認したい、あるいは責任を追及したいという思惑が働くかもしれません。
4. 無断欠勤状態を疑っている
退職代行から会社へ連絡がスムーズに届いていない、あるいは会社が「退職代行の連絡を無視している」という場合には、企業側が「従業員が突然、無断欠勤をしている」と認識する可能性があります。これが長引くと、安否確認や出勤督促を目的として自宅訪問につながる場合があります。
退職代行サービス利用で会社が家に来た場合の対処法

もしも実際に会社が自宅を訪問してきた場合、どう対応すればいいのでしょうか。ここでは、冷静かつ安全に対処するための方法を紹介します。どのような状況であっても、パニックにならず、自分の身を守るためにできる行動をしっかりと理解しておくことが大切です。
1. 玄関先での対面を避け、インターホン越し・電話・メールで対応する
会社の人が来ても、無理にドアを開けて直接会話をする必要はありません。インターホンやドア越しに「退職の意思は既に退職代行サービスを通じて伝えている。詳しいやりとりはすべてそちらにお願いしてほしい」と告げるだけで十分です。対面すると相手の勢いに押され、意図せず話が長引いたり、トラブルに発展したりするリスクが高まります。
2. 退職代行業者へ連絡して状況を説明する
自宅訪問があったことを、できるだけ早く退職代行業者に伝えましょう。業者としても、会社からの不当な行為を把握できれば、改めて会社に対して「自宅への直接訪問はやめてほしい」と要望を伝えやすくなります。弁護士や労働組合が運営している退職代行であれば、法的根拠に基づいてより強い警告をしてもらえるかもしれません。
3. 目的を冷静に確認し、必要に応じて対応する
会社側が訪問してきた目的によっては、すぐに解決できる問題もあるかもしれません。たとえば、単純に会社に返却すべき備品が残っている場合は、着払いの宅配便などで対応すれば足りるでしょう。重要なのは、会社の人と直接会うことなく、退職代行業者などを介して合理的な方法で解決策を模索することです。
4. 不当な威圧や嫌がらせが続く場合は専門家や警察に相談する
もし会社側が「恐喝・脅迫まがいの言動をする」「不退去罪が成立しそうなほど居座る」といった状況になったら、迷わず専門家や警察に相談しましょう。録音・録画などの証拠を残しておくことも重要です。自宅への不当な訪問は、プライバシー侵害やストーカー規制法に触れる可能性があり、あまりに悪質な場合は法的措置が必要になるケースもあります。
自宅訪問を避けるための予防策

会社に自宅へ押しかけられるリスクを可能な限り回避したいのであれば、退職代行サービスを利用する段階で下記のような予防策を講じておくと安心です。トラブルを未然に防ぐためにも、少しでも不安がある方はぜひ確認しておきましょう。
1. 退職代行業者と緊密に連携し、情報を正確に共有する
退職代行に依頼する際には、勤め先の情報や自分の就業状況、貸与物の有無などを正確に伝えることが大切です。情報に食い違いがあると、会社側が「何も聞いていない」「貸与物が返却されていない」として、直接訪問を試みるきっかけになりかねません。些細なことでも業者に相談し、あなたと会社の間に誤解が生じないよう努めましょう。
2. 貸与物や会社所有物は早めに返却する
退職後にPCや制服などの貸与物が手元に残っていると、会社は「直接会って回収したい」と考えることがあります。退職代行に依頼をすると同時に、宅配便などを使って手早く返却することで、会社が家に押しかける理由を減らすことができます。
3. 緊急連絡先や連絡手段を明確に伝えておく
会社がどうしても緊急に連絡を取りたい場合に備えて、「急用や書類のやり取りは退職代行業者を経由してほしい」「連絡はメールか電話に限定してほしい」といったルールを事前に設定してもらうのも有効です。会社がルールを守らない場合、退職代行業者から改めて注意してもらうことで、不要な自宅訪問を牽制できます。
4. 転居や住所非公開も検討する
あまりにも強引な会社であれば、思い切って住所を変えるという手段もあります。ただし、住民票や各種手続きの問題が生じるため、現実的にはハードルが高い対策です。とはいえ、暴力的な脅しが想定されるような場合には、安全確保のために転居を視野に入れるケースもあるでしょう。
5. 万が一の訪問に備え、録音・録画などの手段を準備しておく
自宅に押しかけられたときのために、スマホや録音機を使って会話の内容や状況を記録できるようにしておくと安心です。証拠を残しておけば、後から法的措置を考える際にも役立つ可能性があります。
退職代行サービスの法的問題と権利
「退職代行を使うと法律的に問題があるのでは?」「会社から損害賠償を請求されるんじゃないか?」といった不安を感じる方も少なくありません。結論から言えば、労働者が正当な理由で退職する限り、法律的に大きな問題は生じにくいと考えて大丈夫です。
1. 労働者には自由に退職する権利がある
日本の民法(627条)では、期間の定めのない雇用契約の場合、少なくとも2週間前に退職の意思を示せば、基本的には退職が認められると規定されています。正社員であってもこれは変わりません。会社が「退職届を受け取らない」「退職を認めない」と言っても、労働者が正当な手続きを踏めば退職は成立するのです。
2. 退職代行業者の交渉範囲に注意
一般の退職代行業者は、あなたの退職の意思を伝える「代理人」としての役割は担えますが、法的な交渉(賃金未払いの請求や損害賠償問題など)までは行えない場合がほとんどです。そのため、もし会社との間で金銭的トラブルが懸念される場合は、弁護士が運営する退職代行サービスや労働組合が提供するサービスを利用するのが安心です。
3. 損害賠償を請求されるリスクは低い
会社側が「退職によって損害が出たから賠償しろ」と言ってくるケースはありますが、裁判で認められるかどうかは別問題です。通常、労働者が会社に多額の損害を与えるようなケースは極めて稀であり、退職だけを理由に損害賠償責任が発生することはほとんどありません。心配な場合は、弁護士などに一度相談してみると良いでしょう。
4. 会社による自宅訪問はプライバシー侵害になり得る
強引に自宅に押しかけて、威圧や脅迫を行う行為は、場合によっては不退去罪や住居侵入罪などに該当する可能性があります。自宅というプライベート空間を侵害された場合は、警察や弁護士に相談することで適切な対応を図ることができます。
まとめ:退職代行サービスを賢く利用して、ストレスフリーな退職を実現しよう!
退職する場合に、会社の方が訪問してくるケースはそれほど一般的ではありません。万一会社の人が訪問してきた場合も、冷静に対処法を把握しておけば大きなトラブルになることは少ないでしょう。
もしも今、仕事上の悩みや不満で心身の限界を感じているのなら、一度退職代行サービスの利用を検討してみるのも一つの手段です。 退職を決断することは人生の大きな転機ですが、同時に新しい道へ踏み出すきっかけにもなります。退職代行によってストレスフリーな退職を実現し、その後のキャリアや生活を前向きにスタートできる可能性は大いにあるはずです。
あなたの退職は「逃げ」ではありません。自分自身を守り、より良い未来を築くために取るべき正当な行動です。退職代行サービスをうまく活用しながら、心身の健康とキャリアの充実を両立させ、次のステージへと進んでいきましょう。きっと新たな道が開けるはずです。

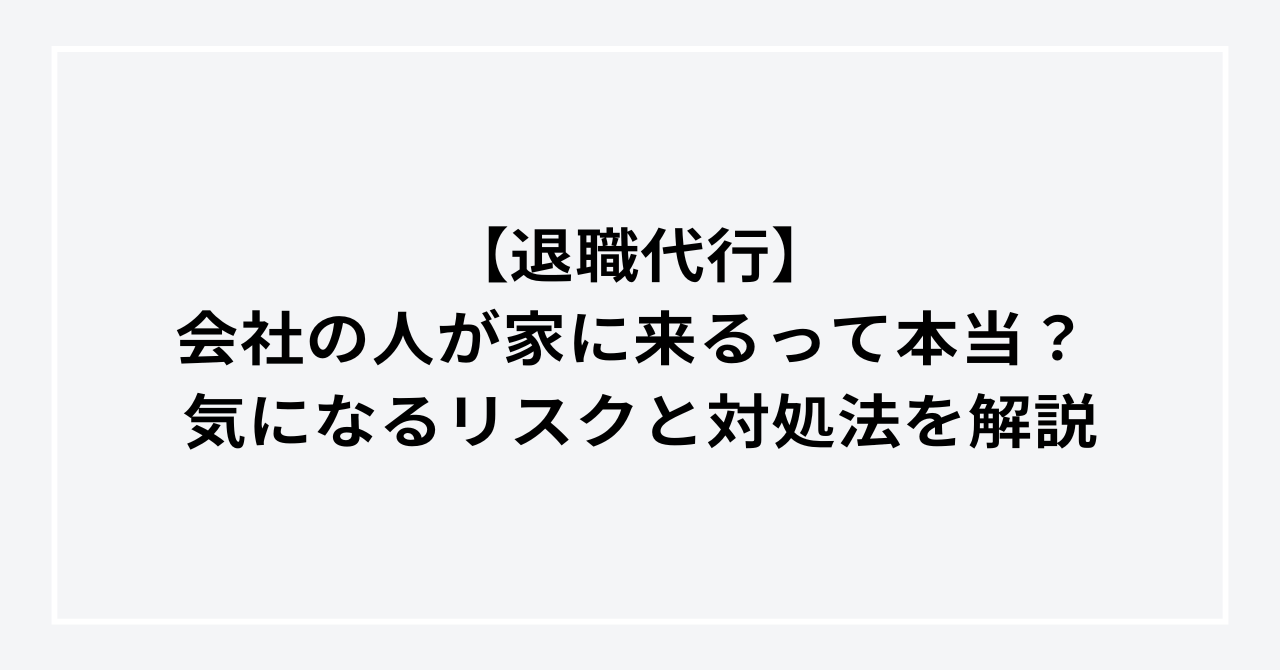

コメント