近年、働き方改革やテレワークなど、社会全体で「働きやすさ」や「ワークライフバランス」に注目が集まる一方で、「辞めたいと思いながら働く」 人が増えています。
2023年の総務省の「労働力調査」によると、年間の転職希望者数は1,700万人に達しました。この結果からも、実際に多くの方が仕事を辞めたいと悩み、新しい仕事への転職を希望しているとわかります。
実際に「仕事辞めたいと思いながら働く」「毎日辞めたいと思いながら働く」というキーワードでインターネット検索をしている方が増えている状況を見ると、同じような悩みを抱える方が決して少なくないことがわかります。
なぜ、このような状況が生まれるのでしょうか。背景には以下のような要因が考えられます。
- 転職市場の活性化: 企業の採用ニーズが高まり、転職がしやすい状況が続いている
- SNS・情報メディアの拡散: 他社・他業界の労働環境を知りやすくなり、自社との比較で不満を持つ
- 働き方の多様化: フリーランスや在宅ワークが一般化し、会社に縛られない働き方への憧れが強まる
こうした情報や選択肢が増えることで、自分の仕事や職場への不満が相対的に大きく感じられるようになり、辞めたい気持ちを抱きつつ働く人が増えていると言えます。しかし、そのまま我慢し続けることには大きなリスクがあり、最悪の場合、心身の健康を損ねる可能性も。ここからは、「辞めたいと思いながら働く」状態の具体的な原因やリスク、そして改善策について詳しく解説します。
「辞めたいと思いながら働く」ことの主な原因
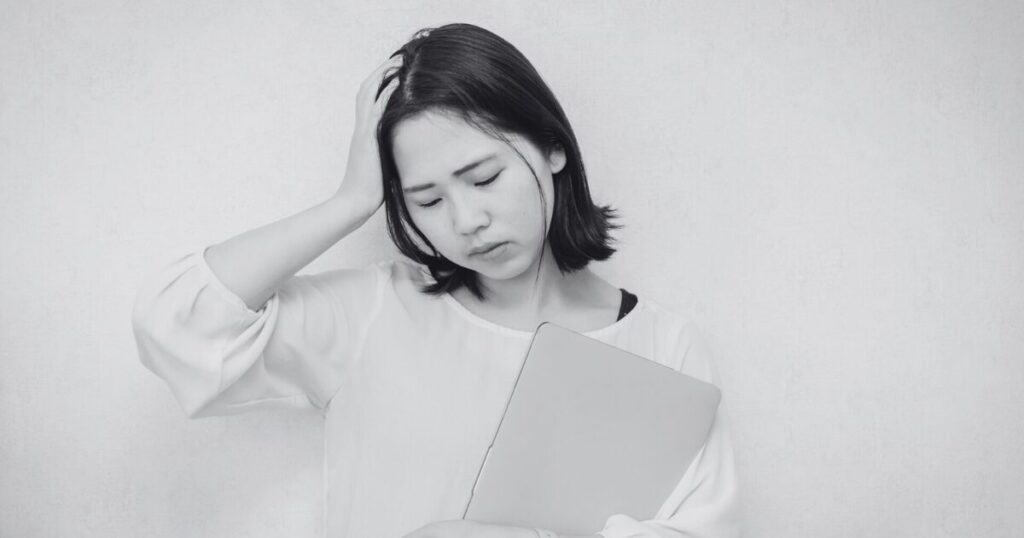
1. 仕事量・残業の多さ
長時間労働やサービス残業が常態化している職場では、心身ともに疲れ切ってしまうケースが少なくありません。休む暇もなく働き続けるうちに、気づかないうちにストレスが蓄積し、「もう辞めたい」「このまま働き続けるのはしんどい」という思いが強まります。
2. 人間関係のトラブル
どんなにやりがいのある仕事でも、上司や同僚との不和や、いじめ・パワハラ・セクハラといった人間関係の問題が起こると、それだけで仕事に行くのが苦痛になります。人間関係の悩みは解決が難しく、我慢を続けるうちに精神的に追い詰められてしまう人も少なくありません。
3. 仕事内容が合わない・適性が感じられない
「やりたい仕事とは違う」「自分の得意分野ではない」など、適性と実際の仕事内容がかけ離れていると、モチベーションは大きく下がります。自分のキャリアを考える上でも、このまま続けるべきかどうか疑問が生じ、辞めたい気持ちにつながります。
4. 評価制度や給与への不満
仕事の成果が正当に評価されない、昇給やボーナスが期待できない、あるいは自分が働いている業界・職種が低賃金の傾向にある――。こうした理由で、「収入面に将来性がない」と感じることも、辞めたい理由の一つです。
5. 将来への不安
会社の業績が思わしくない、業界全体の先行きが不透明など、将来像が描きにくい環境で働いていると、不安がどんどん募ります。「このまま続けてもキャリアアップできないのでは」「もっと安全な道を探した方がいいのでは」と悩み、辞めたい気持ちが膨らみます。
ポイント: 「辞めたいと思いながら働く」原因は複数重なっている場合がほとんどです。まずは自分が何に悩んでいるのかを可視化し、原因を整理することが大切です。
仕事を辞めたいと思いながら働くことのリスクと心身への影響

仕事に対する不満やストレスを抱え、「毎日辞めたいと思いながら働く」状態を放置していると、次のようなリスクが生じます。
1. メンタルヘルスの悪化
強いストレス状態が続くと、うつ病や適応障害などのメンタル不調を引き起こす可能性が高まります。特に、夜に仕事のことを考えて眠れなくなったり、朝起きるのがつらくなったりするのは要注意のサインです。
2. 肉体的な不調
ストレスは精神面だけでなく体にも影響します。頭痛・腹痛・肩こり・慢性疲労など、明確な病名がつかないまま体調不良が続くケースも。悪化すると日常生活に支障が出るだけでなく、仕事のパフォーマンス低下にも直結します。
3. キャリアの停滞
「辞めたい」と思いながら働いていると、仕事そのものに身が入らず、成果が上がらない状態になりがちです。結果的に会社からの評価も得られず、昇進やキャリアアップの機会を逃す要因にもなります。
4. プライベートへの悪影響
仕事の悩みは職場だけにとどまらず、家族や友人との関係にも影響を及ぼします。イライラして当たってしまったり、疲れすぎてコミュニケーションがとれなくなったりすることで、大切なプライベートの時間も楽しめなくなる恐れがあります。
「辞めたい」と感じた時に考えるべき判断基準

1. 自分の優先順位・価値観を整理する
- お金、ワークライフバランス、キャリアアップ、趣味や家族との時間など
- 何を最も重要視するかをはっきりさせる
例えば「給料は少々下がってもいいから、ストレスの少ない環境で働きたい」「多少残業があってもいいから、将来のキャリアにつながる仕事がしたい」など、自分の基準を明確にしましょう。
2. 周囲のアドバイスを取り入れる
家族や友人、同期・先輩など、信頼できる人の客観的な意見を聞くのも有効です。自分では見えていなかった長所や転職の可能性を示唆してもらえることもあります。
3. タイミングを見極める
- ボーナス支給時期
- 入社・異動してからの期間
- 転職先の採用タイミング
金銭面や社会保険の切り替えなど、実務的な観点も含めて考慮しましょう。勢いだけで辞めると、後々困ることが多いです。
4. 今後のキャリアビジョンを考える
- 将来、どんな職業・働き方を目指したいのか
- 必要なスキルや経験は何か
- 会社・業界を変えれば解決するのか
「辞める」か「続ける」かを考えるより先に、自分の理想の将来像を描いてみることで、本当に今の職場に残るべきかが見えてきます。
「辞めたいと思いながら働く」状況を改善する具体策

1. 社内で改善を試みる
- 上司や人事との面談: 業務量の調整や部署異動を打診
- 休暇制度の活用: 有休やリフレッシュ休暇を利用して、一度リセットする
- カウンセリングの利用: 産業医や社外カウンセラーに相談する
会社が従業員の健康を配慮している場合、相談することで前向きに対応してもらえる可能性があります。人事異動や担当業務の変更によって悩みが解消されるケースも珍しくありません。
2. 転職活動を始めてみる
- 転職サイト・エージェントを活用: 自分の市場価値や他企業の実情を知る
- 自己分析とスキルアップ: 資格取得や勉強を通じてキャリアの幅を広げる
「辞めたい」と思う理由が業界の特性や会社の体質によるものなら、転職が有効な解決策となることも。実際に転職活動を行うことで、自分に合った職場を見つけやすくなります。
3. 一時的に休む・休職制度を利用する
心身の健康状態が深刻な場合は、医師の診断書をもとに休職制度を利用する選択肢もあります。休息期間を設けることで、心身を回復させ、じっくりと今後のキャリアを考えられるようになります。
4. 退職代行サービスを視野に入れる
人間関係のトラブルや上司と話すのが苦痛で、退職を切り出すハードルが高いと感じる方は、後述する退職代行サービスの利用も検討する価値があります。どうしても会社とコミュニケーションが取れない状況でも、スムーズに退職できる可能性があります。
退職代行サービスとは?特徴とメリット・デメリット

退職代行サービスの概要
退職代行サービスとは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な手続きをサポートしてくれる専門業者のことです。近年、メディアやSNSでも話題となり、利用者が増えています。弁護士法人や労働組合、民間企業などが運営しており、それぞれサポート内容や料金体系が異なります。
メリット
- 直接会社と話さずに済む
上司や人事担当者に退職を切り出すストレスから解放されます。パワハラなどで悩んでいる場合も、精神的負担が軽減されるでしょう。 - スムーズに退職できる可能性が高い
法的知識に基づいた手続きを行うため、自己流で退職を申し出るよりも円滑に退職できる場合が多いです。 - 即日対応・休日対応など柔軟なサービスがある
退職代行会社によっては、24時間365日対応を行うところもあり、忙しい方でも依頼しやすくなっています。
デメリット
- 費用が発生する
相場としては数万円前後かかります。金銭的負担をどこまで許容できるかが大きな課題です。 - 会社との直接交渉が難しくなる
退職代行業者を通じるため、退職後に発生するトラブルや条件交渉を本人が行いにくくなる可能性があります。
特に有給消化の交渉や残業代の請求など、弁護士資格が必要な交渉領域に関しては、弁護士や労働組合が運営する退職代行会社を選ぶと安心です。 - 会社側の心象が悪くなるリスク
退職代行を利用したことが伝わったときに、職場に残る人や上司からの印象が悪化する可能性があります。ただし、今後その会社と関わらない場合は、さほど気にしなくてもよいでしょう。
注意点: 退職代行サービスを選ぶ際には、運営元が弁護士法人かどうか、料金体系やサポート範囲(有給消化・未払い残業代の交渉など)をしっかり確認しましょう。
まとめ
「辞めたいと思いながら働く」状態を放置することは、心身の健康やキャリア成長の面で大きなリスクを伴います。 まずは自分の悩みの原因を整理し、社内で改善できる方法を探り、それでも難しければ転職や退職を検討するのが現実的です。
とくに、人間関係のトラブルで上司に退職を言い出すのが難しいと感じる方や、精神的に追い込まれていてこれ以上交渉する余裕がない方は、退職代行サービスの利用が一つの解決策となります。外部の専門家に任せることでスムーズに退職の手続きを進められ、次のステップへ進むための時間と心の余裕を得られます。
どの方法を選ぶにしても、行動を起こさなければ何も変わりません。今の仕事で感じるストレスや将来の不安を、できるだけ早く解決して、自分らしいキャリアと豊かな人生を手に入れましょう。




コメント